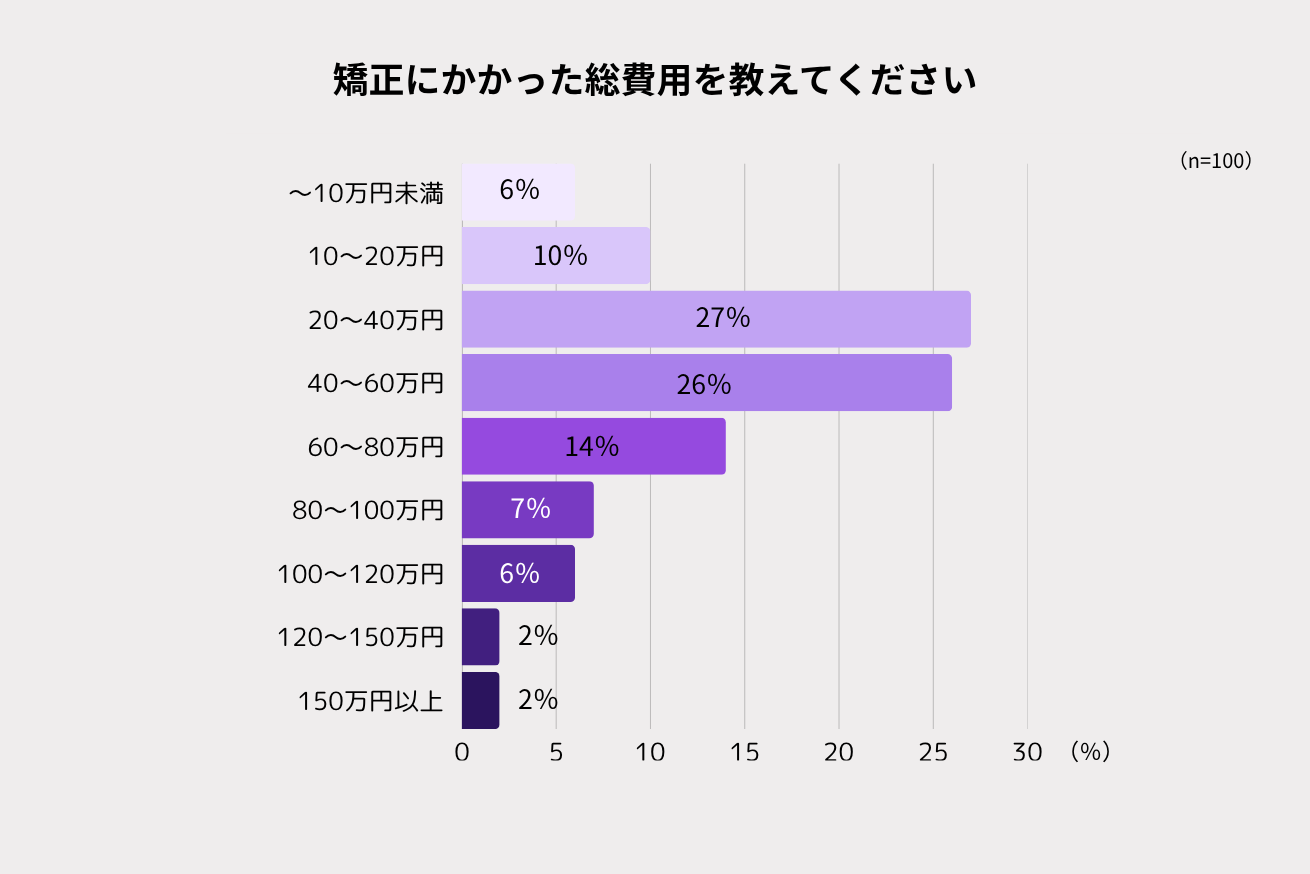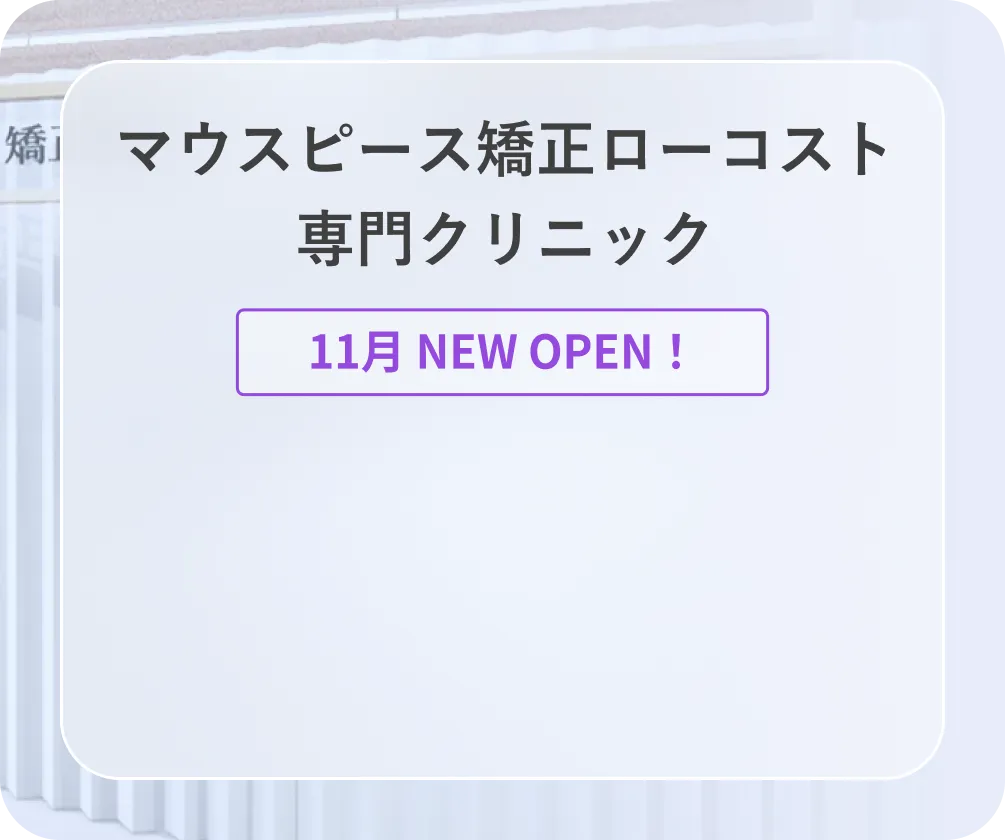記事冒頭で「歯列矯正の治療は全体で約3〜5年程度かかる」と言いましたが、人によっては1年で済む場合もあれば、5年かかる場合もあります。一人一人期間が異なるのはなぜでしょうか?
それは、治療期間が単一要因で決まることはなく、複数の要素が複雑に絡み合って決まるためです。ここでは矯正期間を左右する下記5つの要素について、専門的な視点から解説します。
- 年齢(骨代謝)
- 症例の難易度
- 装置の種類
- 患者の協力度
- 医師の治療方針
年齢(骨代謝)
年齢は、矯正期間に大きな影響を与える要因の1つです。
歯が動く仕組みは、歯を支える骨の吸収と再生、すなわち「骨代謝」に基づいています。一般的に成長期の子供や若年者は骨代謝が活発で、顎骨の成長を利用することで歯を効率的に動かせる傾向にあります。
一方、骨の成長が完了した成人は骨代謝のスピードが緩やかになるため、若年者と比較して歯の移動に時間がかかることが一般的です。もちろん、矯正自体が不可能なわけではなく、適切な治療計画のもとであれば、40代や50代、あるいはそれ以上の年齢でも歯並びを整えることは可能です。
症例の難易度
症例の難易度は、治療期間を左右する最も大きな要因です。
歯並びの問題が、歯の傾きや位置だけに起因する「歯槽性」のものか、顎の骨格の大きさや位置に起因する「骨格性」のものかによって、治療の複雑さと期間は大きく異なります。
例えば、軽度の叢生(ガタガタの歯並び)やすきっ歯など、歯の移動距離が短い場合は比較的短期間で治療が完了します。しかし、歯をきれいに並べるためのスペースがなく抜歯が必要な場合や、噛み合わせが大幅にズレている場合は歯を大きく動かす必要があるため、その分治療期間も長期化します。
特に上顎や下顎が前後左右に大きくズレているといった骨格性の問題(顎変形症)が原因である場合、矯正治療だけでは根本的な改善が難しく、外科手術を併用する必要があります。このような外科的矯正治療は「術前矯正」「外科手術」「術後矯正」という複数のステップを踏むため、トータルの治療期間は3年以上になることも珍しくありません。
装置の種類
矯正治療には、歯の表側または裏側に装置をつけるワイヤー矯正、装置が目立たないマウスピース矯正など様々な種類があります。前述の症例の難易度ほど期間に大きな差はないものの、それぞれ得意とする症例が異なるため、治療期間を最優先する場合は装置の選択が重要になります。
具体的には、ワイヤー矯正は重度の症例を含め適応範囲が広いという利点を持つ一方で、装置が目立つことや痛みを伴うことが難点となります。逆にマウスピース矯正は適応症例が軽度〜中等度に制限されますが、無色透明で装置が目立たず、着け心地も比較的快適というメリットを持っています。
いずれにせよ装置の選択は、歯科医師との相談を十分に行い、どの装置がご自身の症例に対して効率的なのかを吟味することが重要です。
患者の協力度
矯正期間を計画通りに進める上で、患者自身の協力度は極めて重要な要素です。
特にマウスピース矯正を選択した場合、最終的な治療期間は患者の自己管理能力によって大きく左右されます。具体的には、マウスピース矯正は1日20時間〜22時間以上の装着が必須であり、この装着時間を守れなければ歯は計画通りに動かず、治療期間の長期化を招くことになります。
またワイヤー矯正とマウスピース矯正ともに、噛み合わせを調整するために「顎間ゴム」と呼ばれる小さなゴムを患者自身でかける処置が必要になることがあります。こちらも指示通りに行わなければ、歯並びは整っても噛み合わせが改善されず、結果的に治療が長引く原因となります。
これら以外にも、定期通院を怠らないこと、装置の清掃を丁寧に行うこと、口腔内を健康に保つことなど、患者が積極的に治療に協力する姿勢がスムーズな治療を行う上で重要となります。
医師の治療方針
同じ患者の歯並びであっても、担当する歯科医師の診断や治療方針によって、提案される治療計画や期間が異なる場合があります。矯正歯科治療には様々な治療法や考え方が存在しており、どういったアプローチをするかは歯科医師の経験や知識に委ねられる部分が大きい側面があります。
例えば、複雑な症例に対して、ある歯科医師は歯のスペース確保のために抜歯治療を選択するかもしれません。この場合、抜歯の処置に加え、抜歯で生まれた隙間を埋めるための期間が必要になります。
一方で、別の歯科医師は非抜歯治療を選択し、歯列を側方や後方に拡大するなどの方法でスペースを作るかもしれません。こちらのケースでは抜歯を避けられますが、歯の動き方は患者それぞれ異なり、アプローチ方法も複数あるため医師の経験・知識などで治療期間が変わってきます。
最終的な治療開始の判断は患者に託されるわけですが、まずは信頼できる歯科医師を見つけ、提案された治療方針の根拠やメリット・デメリットについて十分な説明を受けることが重要です。そして、納得の上で治療を始めるようにしましょう。
お近くの提携クリニックで
\ 治療期間をチェック /